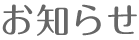高齢者の食事、安全ですか? 〜家庭でも施設でもできる食中毒予防〜
こんにちは!介護士のトン吉です。
季節の移りかわりは早いもので、もうすぐ雨の季節がやってきますね!温度や湿度が上がることで細菌が繁殖しやすくなります。そこで気をつけないといけないのが食中毒です。
今回は食中毒についてのお話です。
年齢を重ねると、体の免疫力や消化機能が弱まり、ちょっとした食べ物のトラブルが命にかかわることもあります。特にこの時期に注意したいのが「食中毒」です。高齢者は発症すると重症化しやすく、回復にも時間がかかるため、日常の食事管理がとても重要になります。
まず、高齢者が食中毒に弱い理由には、胃酸の分泌量が減ることや、体温が上がりにくく初期症状に気づきにくいことが挙げられます。また、水分を摂る力や代謝の低下により、脱水症状が重篤化しやすい傾向もあります。
家庭や施設での基本的な予防策としては、まず「手洗いの徹底」と「調理器具の清潔保持」が挙げられます。食材は購入後できるだけ早く調理し、冷蔵・冷凍保存は適切な温度管理が必要です。加熱調理は中心まで火を通すことが大切で、特に鶏肉や魚介類、卵は注意しましょう。
注意すべき食品としては、生ものや生卵、加熱が不十分な調理品などがあります。また、手作り弁当や作り置き料理は、常温で長時間放置しないようにしましょう。2時間以内に食べきるか、粗熱をとって速やかに冷蔵庫へ入れることが望まれます。トン吉は介護士になる前に調理師をやっておりまして、そこでは閉店後に余った加熱食材は氷水を使って急速冷却を行ってから冷蔵庫に入れていました。食中毒を引き起こす細菌などは、ある一定の条件になると急速に増殖します。その一定の条件の一つが温度です。この温度を急速冷却によって短時間で通過できます。最近はこの急速冷却が出来る高性能の冷蔵庫も出ていますよね!100均などで売っているアルミのトレイなどは便利です。熱伝導率が高いのでトレイに乗せて冷蔵庫に入れるだけで急速冷却出来ます。
食中毒は防げる!〜三原則で守る高齢者の食の安全〜
ここからは食中毒予防の三原則についてのお話です。
高齢になると体の抵抗力や免疫力が低下し、若い人に比べて食中毒にかかりやすく、重症化もしやすくなるということは先程もお話しましたが、高齢家庭でも介護施設でも、安全な食事を提供するためには「食中毒予防の三原則」を意識することがとても大切です。この三原則とは、「つけない・増やさない・やっつける」の3つです。
まず一つ目は「つけない」。これは食中毒の原因となる細菌やウイルスを食材や調理器具に“つけない”ことを意味します。調理や配膳の前には必ず石けんで手を洗いましょう。また、生肉や魚介類を扱った包丁やまな板は、すぐに洗って消毒を行い、他の食材に触れることがないように気をつけます。布巾や台ふきも雑菌の温床になりやすいので、こまめな洗濯や交換が大切です。
二つ目は「増やさない」。細菌は高温多湿(ほとんどの細菌は10~60℃程度で増殖し、36℃前後で最もよく発育します)の環境で一気に増殖します。調理した料理を長時間常温に置いておくのはとても危険です。作り置きの料理はできるだけ早く冷まし、冷蔵庫で保存しましょう。また、冷蔵庫の中も詰め込みすぎると冷気が行き渡らず、菌が増えやすくなります。冷蔵庫の温度は10℃以下、冷凍庫は−15℃以下が目安です。
最後に三つ目は「やっつける」。加熱調理することは最も確実な殺菌方法です。特に肉、魚、卵などの食材は中心部までしっかりと火を通しましょう。トン吉がかつて調理師だった頃に食品衛生の研修へ行ったことがありますが、そこで教わったO157の加熱殺菌の覚え方として…O 157を逆に読むと、75 1 0。75度で1分加熱でゼロと覚えましょう!と教わりました。ね?これは忘れないですよねー?
そしてもう一つ、再加熱する際にも中までしっかり温めることも大切です!調理器具やふきんなどは、定期的に熱湯消毒や漂白を行うとさらに安心です。
これらの三原則は、特別な知識や設備がなくてもすぐに実践できる基本の対策です。大切なのは、「毎日の習慣として続けること」。高齢者の健康を守るために、ご家庭でも施設でも、食事づくりの中でできる小さな工夫を積み重ねていきたいですね!
「いつも通りの食事」でも、ちょっとした油断で健康を損なう可能性がある高齢者の食事管理。大切な人の健康を守るために、今日からできる予防策を見直してみませんか?
最後までお読みいただきありがとうございました!
広報担当 介護士のトン吉でした!